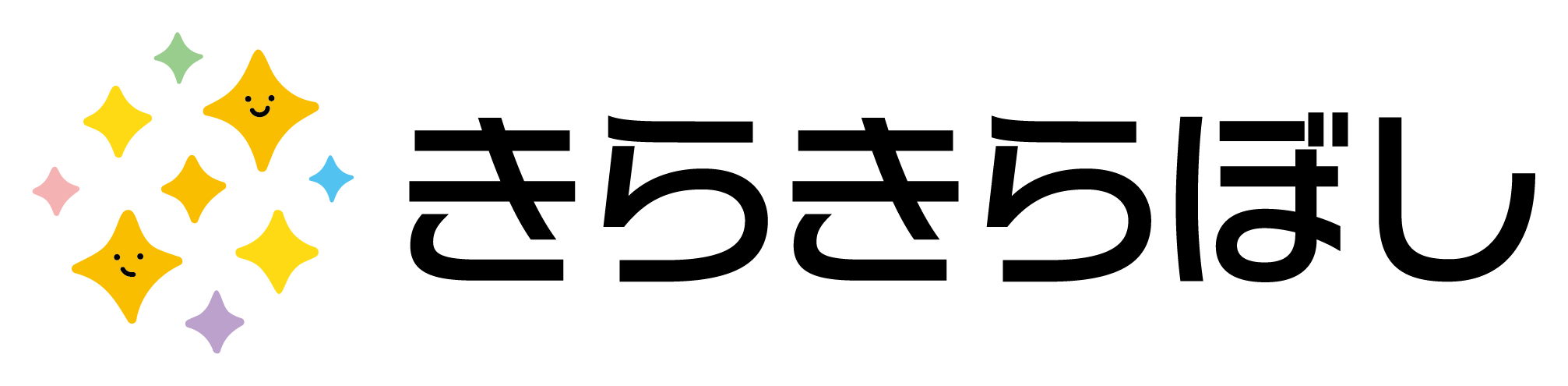みなさん、こんにちは。きらきらぼしです。
先日、この記事を書くきっかけとなったお電話がありました。

ケアが大変で、家のお風呂での入浴は難しくなってきていて困っているんです…。



それは大変ですね…
きらきらぼしでは入浴支援を行なっているので、ご検討されてはいかがでしょうか?



でも入浴って、毎回(自己負担)料金がかかりますか?



入浴支援加算があるので、月8回までは自己負担の上限額内で入浴できます(^^)



えー!そうなんですね★
しらなかった(^^)
こんなやりとりがありました。
まだ入浴支援加算は令和6年度から施行された報酬改定内容で、浸透していない部分も多いようです。
そこで今回はこども家庭庁より発行された、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」を参考にして、入浴支援加算についてご紹介します!
入浴支援加算って何?
入浴支援加算は、医療的ケア児又は重症心身障害児に対して、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定できる加算です。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、児童の発達や日常生活の支援及び家族の支援を目的に創設されました。
月8回を限度に、入浴支援設備を持つ児童発達支援施設・放課後等デイサービスでのサービス提供が可能です。
※9回目以降は各事業所で設定された自費負担額が発生します。
【参照法令等】
報酬告示:別表第1の9の2(児発)、別表第3の7の2(放デイ)
施設基準告示(269):4の2(児発)、10の2(放デイ)
基準告示(270):1の12(児発)、8の4の4(放デイ)
対象者は?
- 医療的ケア児
- 重症心身障がい児
心身に障がいがあり、配慮やケアが必要なお子様、医療的ケアが必要なお子様が対象となっています。
きらきらぼしは、重症心身障がいのあるお子様、医療的ケアが必要なお子様の受け入れが可能です!
条件・要件ってあるの?
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」には以下のような要件が記載されています。
- 安全に入浴させるために必要となる浴室・浴槽・衛生上必要な設備を備え、衛生的な管理を行っていること。
- 障害特性、身体の状況等も十分に踏まえた安全に入浴させるために必要な体制を確保していること。具体的には以下の取組を行うこと。
- 個々の対象児について、その特性等を踏まえた入浴方法や支援の体制・手順などを書面で整理し、支援にあたる従業者に周知すること。
- 入浴機器について、入浴支援を行う日及び定期的に安全性及び衛生面の観点から点検を行うこと。
- 入浴支援にあたる全従業者に対して、定期的に入浴支援の手法や入浴機器の使用方法、突発事故が発生した場合の対応等について研修や訓練等を実施すること。
- 入浴支援の安全確保のための取組その他の必要な事項について、安全計画に位置付け、従業者への周知徹底と当該計画に基づく取組を行うこと。
- 事前に対象児の障害特性、家庭における入浴の状況その他の必要な情報を把握し、これらを踏まえて個別支援計画に位置付けた上で支援を実施すること。
- 安全な入浴のために必要な体制を確保した上で、障害特性や発達段階に応じた適切な方法で支援を実施すること。
参照:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要
また「浴槽を使用した部分浴の場合は算定可。清拭のみの場合は算定不可。シャワー浴は洗身を行う場合には算定可(単にシャワーを浴びせるだけの場合は算定不可)」ともあります。
「入浴することで心身を清潔に、衛生的に保つ」ということは、健康管理にもとても重要ですよね。
まとめ
今回は令和6年度から施行された「入浴支援加算」についてご紹介しました。
「ツルッと滑って溺れないだろうか」
「呼吸器のチューブが外れてしまったらどうしよう」
「入浴中に吸引が必要になっても、私一人でお風呂に入れているのに…」
重症心身障がいがあったり、医療的ケアが必要だったりするお子様の入浴は、保護者様だけでなく看護師さんやヘルパーさんなど支援するケアスタッフにも上記のような精神的・身体的な不安が付きまといますよね。
きらきらぼしでは、お子様一人ひとりの身体状況に合った浴槽や入浴方法を検討しており、安心して入浴を楽しんでいただけます。
- だんだん年齢も重ねて、身体が大きくなったので親での入浴介助が大変。
- 医療的ケアが必要で、自宅での入浴が難しいと感じている。
このようなお悩みがある方は、ぜひ一度きらきらぼしまでお問い合わせください。
当事業所の入浴設備をご覧いただき、事業所の雰囲気を見て、感じていただければと思います(^^)